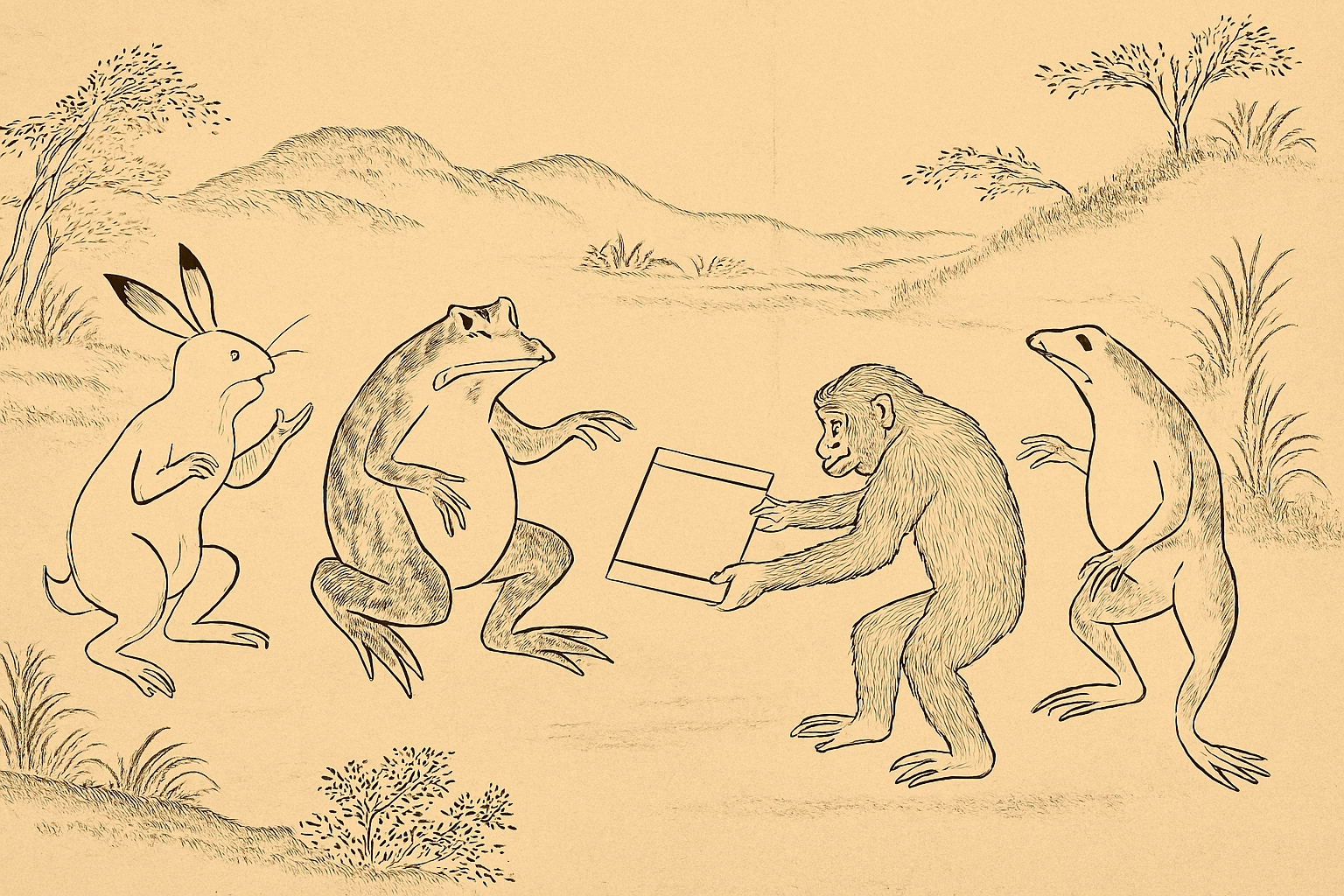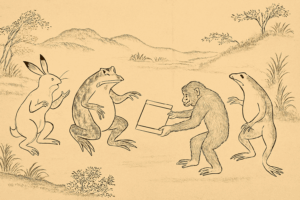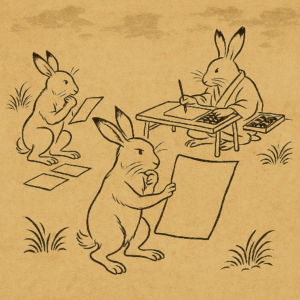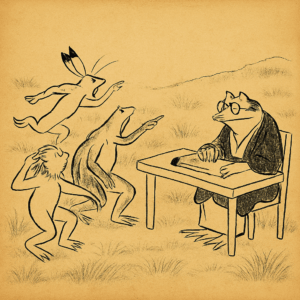顧問料って、なんでこんなに分かりにくいのか
サービスを使うときって、まず料金を見ませんか。
美容院でも、携帯でも。
いくらか分からなければ安心できないのは当たり前です。
でも税理士業界は違います。
まるで“時価の寿司屋”みたいに、頼んでみないと値段が分からない世界がまだ残っているんです。
前に勤めていた事務所では、顧問料が所長の気分で決まっていました。
昨日は「月3万」と言っていたのに、翌日には「やっぱり5万」。
横で聞いていて「基準どこ?」と正直思いました。
独立してから他の事務所のホームページをいろいろ見ましたが、料金を公開しているところはほとんどありません。
そもそもHPがない事務所も多い。
あっても「まずはご相談ください」だけ。依頼する立場なら、不安になりますよね。
見てきた中で分かりにくい理由
僕が見てきた中では、大きく三つ理由があります。
一つ目は、料金が公開されていないこと。
問い合わせをしないと分からない。依頼者からすればハードルが高いです。
二つ目は、売上で区切るやり方。
売上が多いと自動的に料金も高くなる。
でも実際の作業量は会社によって大きく違います。
三つ目は、オプション方式。
月額は安く見えても、年末調整や法定調書など必ず必要な業務が「別料金」。
携帯料金と同じで、「なんだかんだで結局高い」仕組みになってしまう。
僕自身、こういう仕組みが苦手でした。
料金が分かりにくいと、お願いする側も安心できないと思うからです。
それに、見積もり制にすると「安くなりませんか」と言われることもある。
言われた瞬間テンションが下がるし、交渉に時間を取られるのも性に合わない。
だから僕は最初から基準を出しています。
(この考え方は、営業しない税理士の生き方の記事でも触れています。)
僕はこうやって決めている
僕は「面談回数」で料金を分けるようにしました。
年間に必要な業務は全部込み。相談の頻度だけが顧問料の差になる仕組みです。
これなら「何にいくらかかるのか」が最初から分かるし、後から追加される心配もない。
状況によって面談を減らせば顧問料を下げることもできる。柔軟に調整できる形です。
僕は携帯料金みたいに「後から上乗せされて、気づいたら高くなってる」仕組みが昔から嫌いです。
だから自分のサービスでは、そうならないようにしました。
最初から全部込みで提示して、シンプルに。
その方が、僕にとってもお客さんにとっても余計なストレスがないと思うんです。
実際の料金表はこちらです。