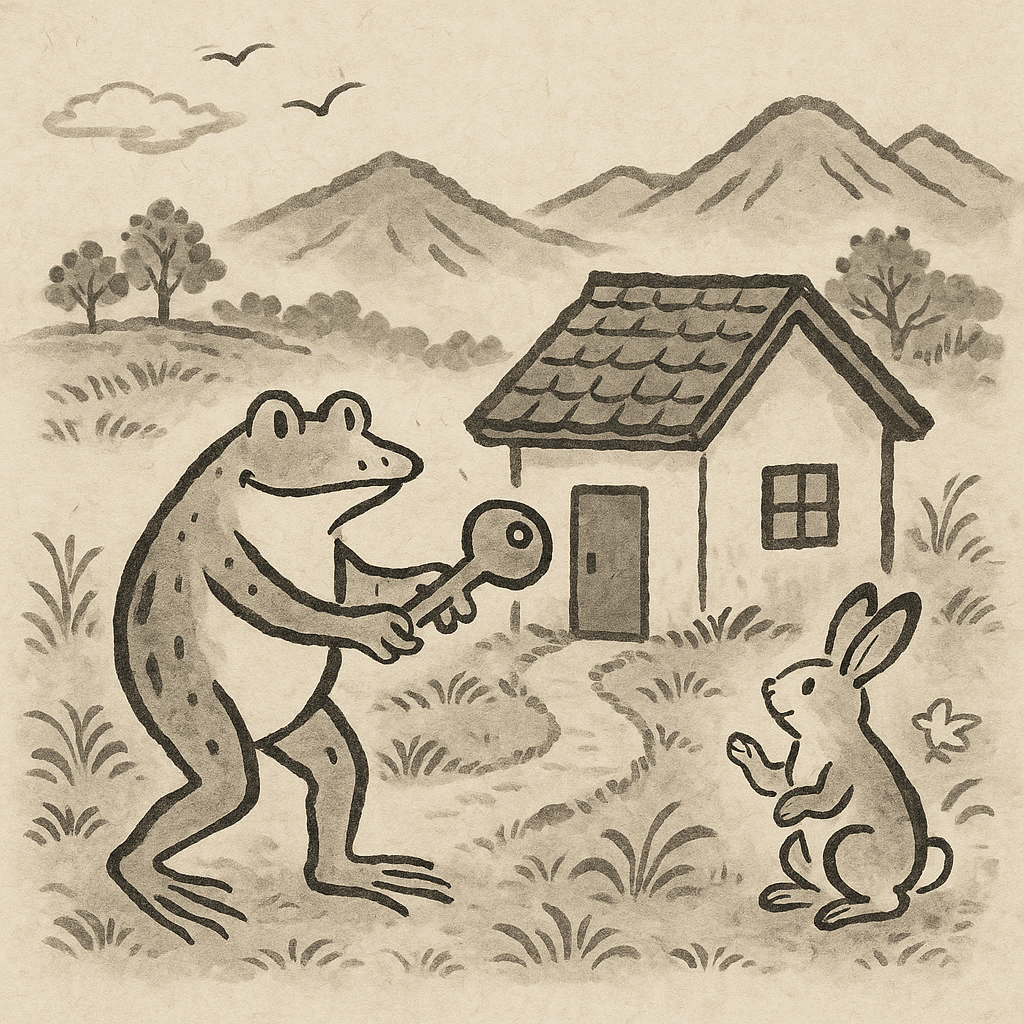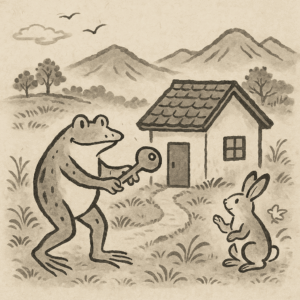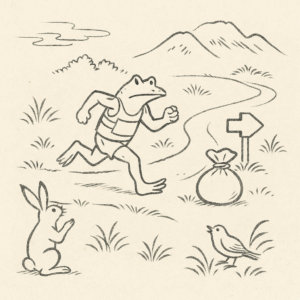独立して会社を作った。
社員は自分ひとり。
そんなときに気になるのが「家賃を経費にできないのかな?」ということです。
結論からいうと、ひとり社長でも社宅化は可能です。
法人なら当たり前の仕組みで、大企業に限った話ではないのです。
社宅ってどんな仕組み?
社宅と聞くと「大企業の社員寮」や「会社がまとめて借りる物件」を想像しがちです。
でも、税法上はもっとシンプル。
会社が借りた家を役員や社員に貸す制度。
社員が社長ひとりでも、この制度を使うことができます。
「ひとりだとダメなんじゃ?」と思われがちですが、実務では問題ありません。
むしろ小規模法人ほどメリットを得やすい制度でしょう。
社宅化のメリット
一番のメリットは節税です。
たとえば、毎月10万円の家賃を払っているとします。
個人で払えば生活費ですが、社宅化すると仕組みが変わります。
- 会社がオーナーに家賃を払う
- 社長が会社に「賃貸料相当額」を払う
- 差額は会社の経費になる
ざっくりいうと、半分〜7割くらいが会社の経費にできるケースが多いです。
年間で60〜80万円程度、利益を圧縮できる可能性があります。
法人税が30%なら、20万円以上の節税効果。
しかも生活費の負担も軽くなるので、キャッシュフロー的にも楽になります。
もうひとつは経理の整理。
「家賃は会社」「水道光熱費は個人」と分けられるので、プライベートと事業のお金が混ざらなくなるのです。
実務でやること
いいことばかりに見えますが、ルールを守る必要があります。
- 賃貸料相当額の計算
税務署が定める基準があります。
床面積、固定資産税評価額、家賃相場などをもとに計算します。
少なく払いすぎると差額が給与扱いになるので要注意です。 - 社宅規程の整備
「どういう条件で社宅を貸すか」を決めた規程が必要です。
形式的でもいいので、必ず文書にして保存しておきましょう。
ひとり社長でも作っておけば安心です。 - 契約と仕訳
賃貸契約が会社名義なら、そのまま会社が支払います。
個人名義でも、会社が立替えて処理することは可能です。
仕訳イメージ(家賃10万円、賃貸料相当額3万円の場合)
会社が払うとき
借方:地代家賃 10万円 / 貸方:現金預金 10万円
社長からの負担分
借方:現金預金 3万円 / 貸方:地代家賃 3万円
最終的に経費になるのは「7万円」です。
まとめ
ひとり社長でも社宅化はできる。
むしろ自宅で仕事をしている社長こそ、メリットを享受しやすい制度です。
- 節税になる
- 経理が整理される
- キャッシュフローも改善する
手間は「規程を作る」「計算する」くらい。
やってみると、意外にシンプルな仕組みなのです。